公開日:2025年8月26日
更新日:2025年9月1日
「子どもにどう教える?」いまどきのお金教育の始め方
監修:森重 幹斗
アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー
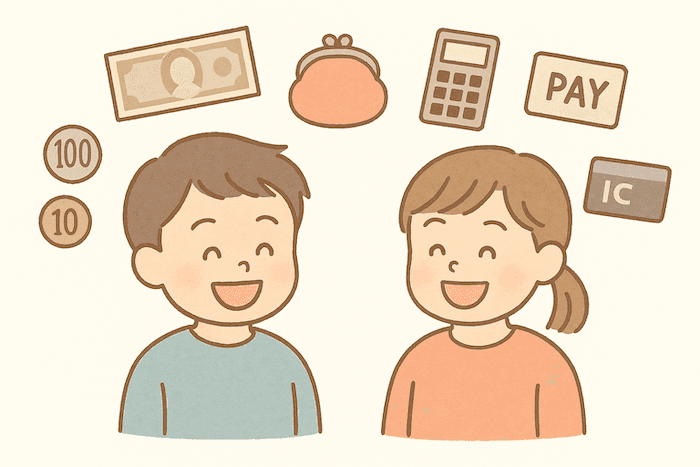
子どもにお金の教育はいつから始めるべき?「難しそう」「まだ早いかな」と思うママ・パパも多いはず。実は、日常のちょっとした工夫でお金教育は無理なくスタートできます。本記事では、働く親が押さえておきたい基本と、今すぐできる子どものお金の教え方をご紹介します。
1. なぜ今、子どもにお金教育が必要?
キャッシュレス決済が普及し、「お金の見えない化」が進む現代。学校教育でも金融教育が必修になりましたが、日常生活での理解が不可欠です。子どもが将来、自分でお金を管理し、計画的に使えるようになるには、早いうちから金銭感覚を育てることが大切です。
お金の教育は、単に「貯金」や「節約」を教えるだけでなく、社会の仕組みや働くことの意味を理解する入口にもなります。
2. どうやって始める?家庭でできるお金教育の始め方
「まだ早いかな?」と思っても、お金の教育は幼児期から始められます。特別な教材は不要。日常の中で「なぜ?」に答えるだけで十分です。たとえば、買い物で「このお菓子は100円だから、2つで200円だね」と声をかけたり、親の仕事を「パパ・ママは働いてお金をもらっているんだよ」と話すことからスタートしましょう。幼児期は「お金は有限」「働くとお金が入る」感覚を伝えるのがポイント。成長に合わせて段階的に広げるのが理想です。
※クイズ形式で遊び感覚で学べる教材もあります。詳しくは【標準講義資料_小学生低学年向け】おこづかいからまなぶお金の話(出典:J-FLEC(金融経済教育推進機構))をご覧ください。
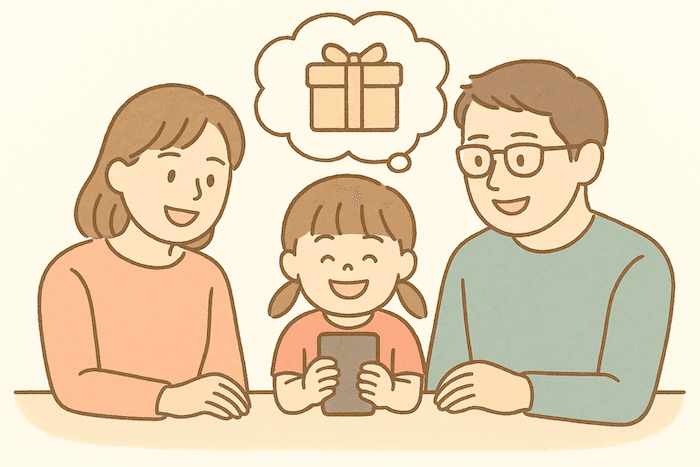
3. お小遣いとキャッシュレス時代の教え方
特に幼児期(就学前)から小学生にかけては、お小遣いが金銭感覚を育てる実践のチャンスです。 目安は低学年で月500円前後と言われています。渡し方は「定額制」が一般的ですが、「報酬制」や「一括制」など、お小遣いの目的や家庭の方針によりさまざまな方式が考えられます。
| 方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 定額制 | 毎月(または毎週)決まった金額を渡す | 計画的に使う習慣が身につく | 金額設定が重要。年齢や使い道に応じて調整が必要 |
| 報酬制 | お手伝いやテストの結果などに応じて渡す | 努力の対価としての意識が育つ | 報酬が目的になりすぎないようにバランスが大事 |
| 一括制 | 1年分や学期分など、長期間のお小遣いをまとめて一度に渡す | 長期的な金銭管理能力が育つ | 最初に使いすぎてしまうリスクがあるので、サポートが必要 |
| 都度制 | 必要なときに都度渡す | 無駄遣いを防ぎやすい | お金の管理能力が育ちにくい可能性も |
管理にはお小遣い帳やスマホアプリを活用すると、計画性が育ちます。さらに、キャッシュレス時代に備えて、ICカードや電子マネーで小額を使わせる体験も有効。「お金は見えなくても減る」という感覚を親子で確認しましょう。
4. 親が意識したい3つのポイント
1. 価値観を伝える
「お金だけが目的じゃないよ」「働くことは社会の役に立つこと」など、親の考えを共有しましょう。
2. 計画性を学ばせる
「欲しい物はすぐ買わず、次のお小遣いまで待つ」ことで我慢と計画力を育みます。
3. 失敗もチャンスにする
「お小遣いを全部使ってしまった!」そんな時は「次はどうすればいいかな?」と一緒に考え、経験から学ばせましょう。お金の教育は完璧に管理するより、親子で考える機会を増やすことが大切です。
まとめ
子どものお金教育は、難しい特別授業ではなく、日常会話や小さな実体験から始められます。早めにスタートすることで、将来の安心と自立につながります。今日から親子で一歩踏み出してみませんか?
私たちは、これからもサイト内のコンテンツを通して、子育て世代の不安を減らし、安心をサポートする情報をお届けします。ぜひ、今後の記事も参考にしてみてください。


