公開日:2025年9月1日
更新日:2025年9月1日
【初心者向け】教育資金を効率的に!投資と貯蓄の基礎のキ
監修:森重 幹斗
アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー
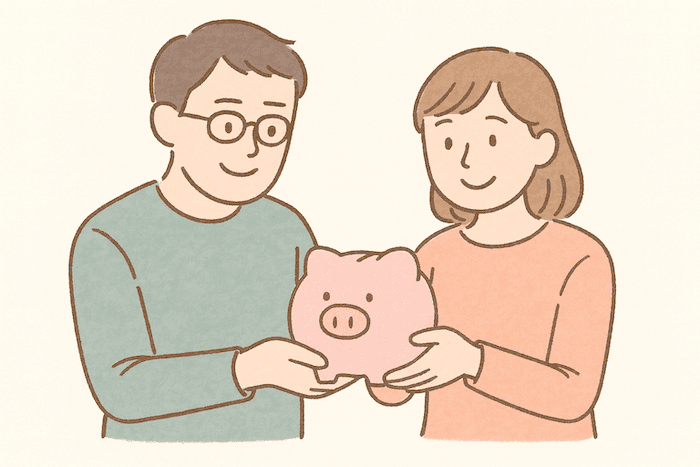
教育資金は、将来のライフプランニングにおいて最も重要なテーマの一つです。幼稚園から大学までの進学ルートによって、教育費は平均で500万円~1,000万円以上必要といわれています。
特に大学進学時はまとまったお金が必要になるため、「どうやって準備するか」は子育て世代にとって大きな課題です。
この記事では、教育資金の平均額、無理なく貯める方法、さらに教育資金として投資を活用するポイントまで、初心者向けにわかりやすく解説します。
1. 教育資金はいくら必要?公立・私立の平均と貯め方
文部科学省の調査によると、教育費の平均額は公立中心で約500万円、私立を含むと1,000万円以上になるケースもあります。
特に大学は高額で、国公立でも入学から卒業までに約250万円、私立文系で約400万円、私立理系では500万円を超えることも珍しくありません。
早めに必要額の目安を知ることで、「どれくらい毎月貯めればいいか」「投資を組み合わせるべきか」が見えてきます。
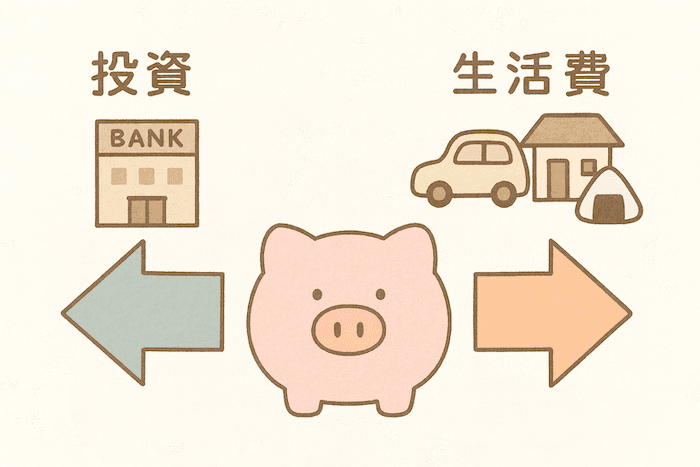
2. 教育資金の貯蓄をラクに続ける家計管理の仕組み
2-1. 先取り貯蓄で教育資金を確実に積み立てる
教育資金を貯めるなら、「余ったら貯める」ではなく、「先に貯める」が鉄則です。
給料日後に自動振替で教育資金専用口座に移す仕組みを作れば、手間なく継続できます。たとえば月5,000円でも、0歳から始めれば小学校入学までに約40万円。さらに、積立NISAを組み合わせれば効率よく増やすことも可能です。
2-2. 家計簿アプリで教育費と生活費を見える化
どれだけ貯められるかを把握するには、支出の見える化が欠かせません。家計簿アプリを使えば、銀行口座やクレジットカードと連携し、自動で記録してくれます。
教育費の割合や無駄な支出を把握すれば、「ここを削って貯蓄に回そう」という改善ができます。
3. 教育資金を投資で効率的に増やす方法【新NISA・学資保険】
教育資金を効率よく準備するには、貯金だけでなく「投資」の選択肢も検討することが大切です。ここでは、2024年にスタートした新NISA制度(つみたて投資枠)と、従来からある学資保険について、それぞれの特徴をやさしく解説します。
・新NISA(つみたて投資枠)とは?
新NISAは、国が定めた投資の利益が非課税になる制度で、2024年から恒久化されました。
新NISAには成長投資枠とつみたて投資枠があり、中でも「つみたて投資枠」は、少額からコツコツ長期で投資したい人にぴったりです。
【主な特徴(つみたて投資枠)】
・年間120万円まで、つみたて枠で非課税投資が可能
・金融庁が認めた投資信託のみ対象なので、初心者にも安心
・最長無期限で非課税運用ができる
・毎月少額から始められる手軽さ
たとえば、月1万円を年利3%で18年間積み立てた場合、約290万円になるという試算もあります(元本216万円+運用益約70万円)。ただし、元本保証はないため、教育資金のすべてを投資に頼らず、バランスが大切です。
参考:金融庁【つみたてシミュレーター】
・学資保険とは?
学資保険は、子どもの進学時期に合わせて満期金や祝い金を受け取れる、保険と貯蓄を兼ねた商品です。
【主な特徴】
・毎月保険料を支払い、契約期間満了時にまとまったお金を受け取れる
・多くの商品では、契約者(親)に万が一のことがあった場合、保険料の支払いが免除される仕組みつき
・満期まで解約しなければ、元本割れのリスクは低い
ただし、インフレに弱く、途中解約すると支払った金額を下回ることがあります。また、保険料や受け取りタイミングなどは商品によって異なるため、契約前に内容をしっかり確認することが重要です。
| 項目 | 新NISA(つみたて投資枠) | 学資保険 |
|---|---|---|
| 非課税制度 | あり(恒久化) | なし |
| 元本保証 | なし | なし |
| 柔軟性 | 金額変更・売却可能 | 解約は損失リスクあり |
| リターン期待 | 年3~5%(実績ベース) | 年0~1%台 |
| 向いている人 | 資金を少しでも増やしたい人 | 安全性を重視する人 |
※詳しくは、【標準講義資料_若手層社会人向け】社会人として知っておきたいお金の話(出典:J-FLEC(金融経済教育推進機構))をご覧ください。
どちらを選ぶかは、「何を重視するか」で異なります。
たとえば「強制力がほしい」なら学資保険、「柔軟性とリターンを求めたい」なら新NISAが向いています。両方を組み合わせて使う家庭も多いです。
4. こども口座の活用術!
教育資金は、親の口座と分けて管理する方がわかりやすく、計画的に貯めやすくなります。お祝い金や児童手当を子ども専用口座に入金し、自動積立を設定すれば、日常の負担も減ります。
さらに、親子で口座残高を確認する習慣を作れば、自然と「お金を貯める感覚」を学べます。「あと○円で絵本が買えるね」など身近な例えを使うと、子どもに数字にリアルな感覚を持たせやすくなります。
まとめ
教育資金づくりは、①必要額を知る、②先取り貯蓄と見える化で仕組みを作る、③投資で効率的に増やす、④こども口座で管理と教育。この4つを押さえれば、将来の不安をぐっと減らせます。
大切なのは、「完璧を目指すより、一歩を踏み出すこと」です。少額からでもOK。子どもの未来のために、今日からできることを始めてみましょう。
当サイトでは、これからも子育て世代の教育資金づくりやライフプランに役立つ情報を発信し、あなたの子育てをサポートしていきます。


